| 横須賀・久里浜 内科・漢方内科 |
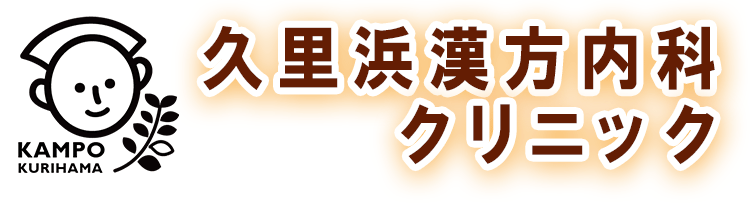 |
|
ドクターコラム
|
|
巷で健康に良いとされ、昔から使われてきた薬草について、述べてみたいと思います。
|
| 民間薬と漢方薬 |
|
中国ではその匂いから魚腥草(ぎょせいそう)と呼ばれ、煎じ薬として、動脈硬化、便秘、整腸、蓄膿症、あせも、痔などに用いられてきました。 (2)ハブ(決明子:けつめいし) 煎じて飲むと、胃腸を丈夫にし便通にも良いとされています。神農本草経(しんのうほんぞうきょう)には、上品(じょうほん)に収載され、目を明るくするとされ、これが決明子の名の由来とされています。様々な眼病に有効とされています。 (3)ハトムギ(○苡仁:よくいにん) 神農本草経の上品に収載されています。毎日服用すると、便通を整え尿をよく出し、皮膚を綺麗にし、胃腸の調子を整え、関節の痛みや疲労回復などの効果があるとされています。(○=くさかんむりに意) (4)ヨモギ(艾葉:がいよう) 「艾」という字は「治す草」という意味があり、名医別録という本には「醫草」という別名が付けられています。止血、鎮痛、抗菌作用があるとされ、漢方薬では、○帰膠艾湯(きゅうききょうがいとう)に用いられています。(○=くさかんむりに弓) (5)シソ(紫蘇) 紫蘇の蘇は、「酥:そ」と同様に、のびのびとして気を巡らし血を和らげる作用があるとされています。魚毒を消す作用があり、刺身によく添えられています。虚証の感冒に用い、漢方では「和剤局方」の香蘇散に用いられています。< (6)イチョウ イチョウは恐竜時代から存在する原始的な木で、フランスのショーサ先生の報告によると、血圧を下げ、動脈硬化に効果があるとされています。 (7)クコ(枸杞) 神農本草経の上品に収載され、実は枸杞子(くこし)、根は地骨皮(じこっぴ)として強壮剤として用いらえています。補腎効果、肝保護作用があるとされ、腰痛、無力感などの「腎虚:じんきょ」に応用されています。 (8)柿のヘタ(柿蔕:してい) 生の柿は邪熱を冷ますため、酒毒を消すとされ、柿のヘタを煎じた柿蔕湯(していとう)は、「しゃっくり」の特効薬として用いられています。 (9)陳皮(ちんぴ) 神農本草経の上品に「橘」として収載され、生薬としては、陳皮、橘皮(きっぴ)、青皮(せいひ)として用いられています。日本では温州みかんの皮の乾燥品を陳皮として多く用いられています。 (10)センブリ 千回煎じても苦い事からセンブリの名前が付けられた、日本でよく用いられる民間薬です。日本以外にも、インドのアーユルベーダやチベット医学で用いられています。リンドウ科センブリの黄色い花が咲いた頃の全草を用います。センブリは「当にこれぞ薬たるべし」という意味で「当薬(とうやく)」とも呼ばれています。 (11)ゲンノショウコ 別名をホッケバナ、レンゲソウ、玄草や老鸛草(ろうかんそう:鸛はこうのとりの意味)と呼ばれ、煎じて飲むと、便秘にも下痢にも効くとされ、民間で健胃、整腸薬として利用されています。 (12)琵琶葉(びわよう) 昔、長州藩の秘伝の名薬として琵琶葉湯があり、腹痛や二日酔いに効果があったとされています。琵琶の葉を煎じて入浴剤に用いると、皮膚炎やあせもに効果があります。 (13)センナ センナは世界最古の医学文書「エーベルス・パピルス」に収載されています。原産地はナイル河流域、インド南部で便秘薬として有名です。 (14)アロエ 生薬名は「○會:ろえ」であり、中国の宗の時代の「開宝本草」に収載されています。アロエはギリシャ語、民間では「医者いらず」という別名で呼ばれ、健胃薬、便秘薬、外傷やヤケドなどに用いられています。(○=くさかんむりに慮)。 (15)雪の下(ユキノシタ) 中国名は虎耳草(こじそう)。耳の形をしているので耳の病気に効くという事らしく、化膿性中耳炎に効果があるとされています。民間では、擦った青汁を耳の中に入れて用いるそうです。煎じ薬は解熱剤として、生の葉を炙ったものを皮膚炎やしもやけに用います。 ◇ ◇ ◇ 院長 小野村 |
|
|
